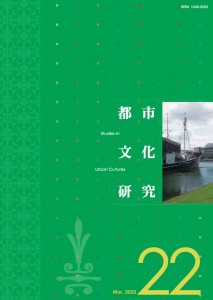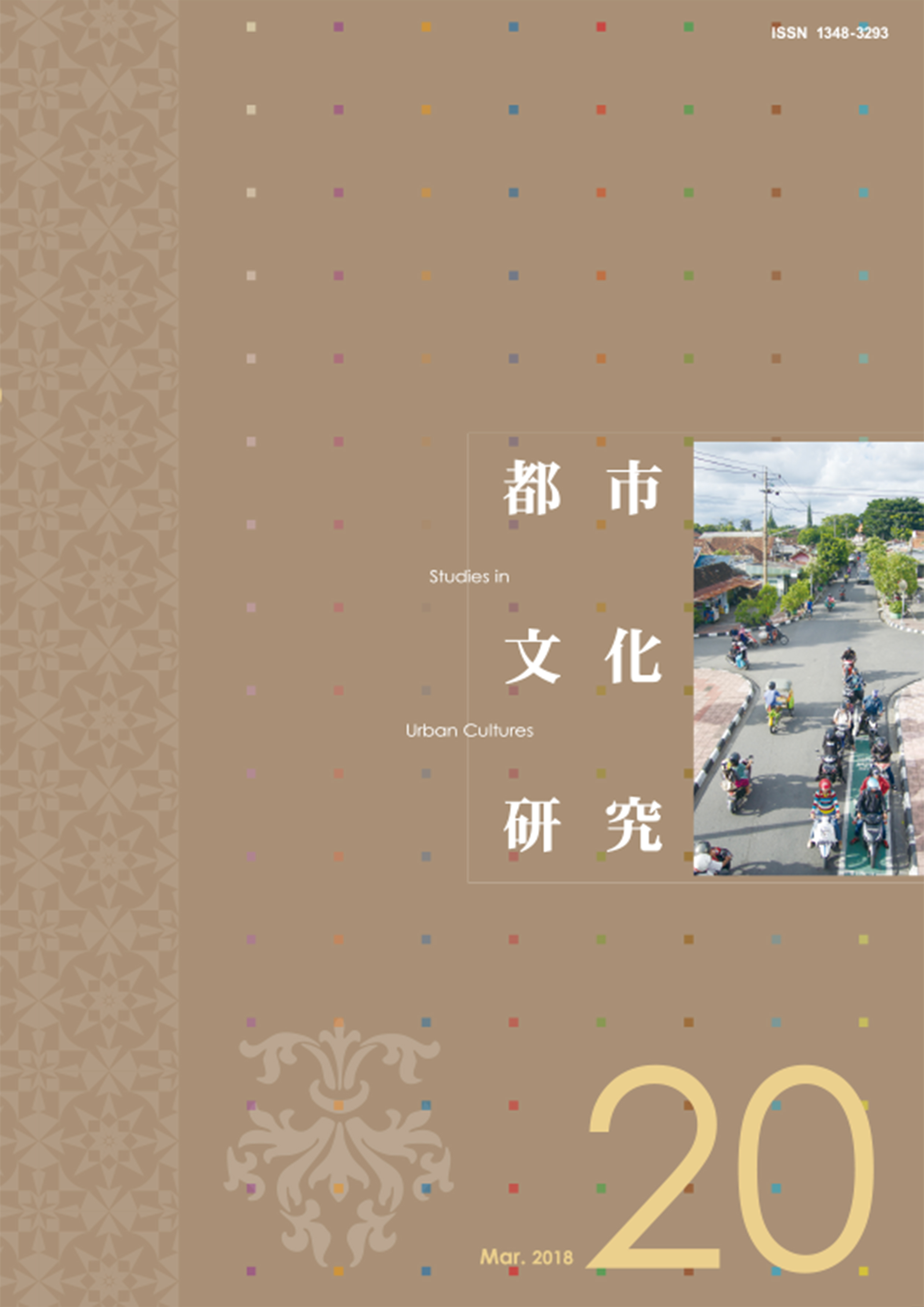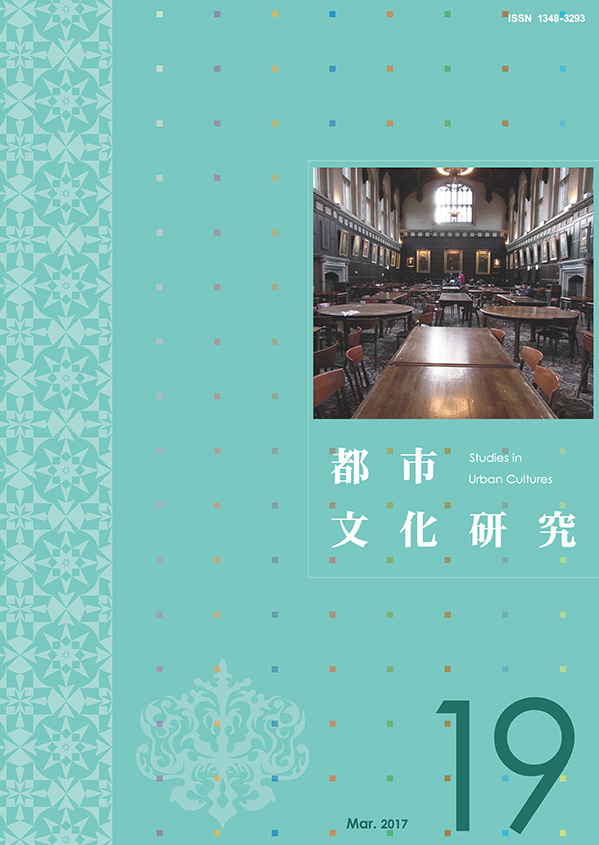このたび、都市文化研究センターは、『都市文化研究』23号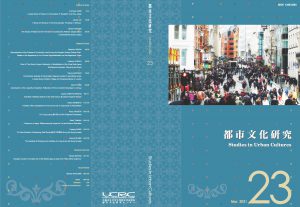
を刊行いたしました。
各掲載論文については、機関リポジトリよりご覧になることができます。
【バックナンバー】項目の「大阪市立大学学術機関リポジトリ」タブからご覧ください。
『都市文化研究』は、都市と文化に関する研究成果を公表することを、主たる目的として創刊された学術雑誌です。
編集委員会では、今後も国内外に読者を広げるべく努力をしていきます。
何卒ご高覧の上、関係方面への周知・講読のご推薦をお願い申し上げます。
なお現在、次号『都市文化研究』24号への投稿エントリーを承っております(こちらよりご確認いただけます)。